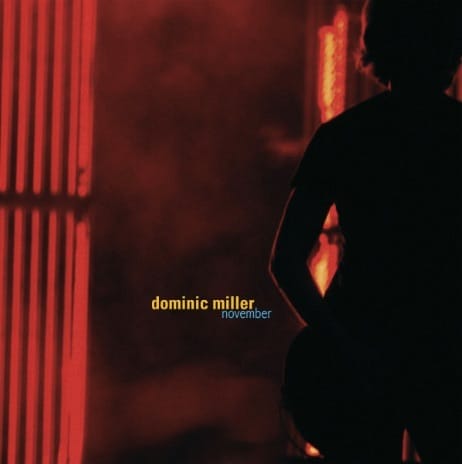■ November ■
■ Musicians ■
■ Dominic Miller(ドミニク・ミラー):G,Key(Tracks/1,3-5,8-10) ■ Mark King (マーク・キング):Ba/Tracks(1-3,5,6-9,11) ■ Ian Thomas(イアン・トーマス):Ds ■ Mike Lindup(マイク・リンダップ):Key,Syn[Moog],Piano/Tracks(1-3,5,6-9,11) ■ David Heath (デヴィッド・ヒース):Flute/Tracks(5) ■ Yaron Herman(ヤーロン・ハーマン):Electric Piano,Syn/Tracks(1,4,5,7) ■ Jason Rebello(ジェイソン・リベロ):Piano/Tracks(8) ■ Lawrence Cottle(ローレンス・コットル) :Ba/Tracks(4) ■ Stan Sulzmann (スタン・シュルツマン) :Sax/Tracks(9) (Drums on Credit 'Machine':Tracks 4,10) ・Recording - Sofa Sound (London) ・Producer - Dominic Miller/Hugh Padgham ・Mixed By – Hugh Padgham ・Mastered by - Tony Cousins ・Engineer – Cesar Gimeno Lavin
■ Songs(CD,Album) ■
01. Solent(4:58) 02. W3(3:32) 03. Still(4:34) 04. Gut Feeling(4:34) 05. Ripped Nylon 06. Racine(4:21) 06. Sharp Object(4:05) 07. Chanson I(4:32) 08. Marignane(3:33) 09. Chanson II(3:06) 10. November(5:40) All Songs:by Dominic MIller
■ Songs(2LP-Ltd Edition) ■
A1. November Reprise(1:45) A2. Solent(4:58) A3. W3(3:32) A4. Chanson I(4:32) B1. Gut Feeling(4:34) B2. Ripped Nylon(3:25) B3. Racine(4:21) B4. Chanson II(3:06) C1. Bachiana No.5(2:18) C2. Sharp Object(4:05) C3. Chanson II Reprise(3:11) D1. Marignane(3:33) D2. Still(4:34) D3. November(5:40) All Songs:by Dominic MIller,Except Track(C1)by Heitor Villa Lobos
■ Release ■
■ Release Date:2010 ■ Rabel:Q-Rious Music(Ger,US) ■ Number:QRM 113-2 ■ CD,Album,Digipack ------------------------------------- ■ Release Date:2010 ■ Rabel:Q-Rious Music(Italy) ■ Number:3000333 ■ CD,Album ------------------------------------- ■ Release Date:2010 ■ Rabel:Q-Rious Music(Ger) ■ Number:QRM 114-2 ■ 2LP-Ltd.Edition
Commentary
このアルバムの制作背景
2010年リリースのドミニクの6枚目のソロアルバムです。今までずっとアコースティック・ナイロン弦の『キング』として作品を作ってきたドミニクが、全編エレクトリックギターをメインに出したアルバムです。
突然エレキギターを持った理由として、ドミニクはインタビューでこう言ってます。
「私は、アコースティック・ギター、特にナイロン弦ギターを演奏すること、そしてそのような作曲スタイルという、私がよく知っている快適なものから離れたかった。ただそこから逃げたかっただけです。年齢のせいもあると思いますが、そろそろ時期が来たと感じました。時々私はこれを中年の危機のアルバムと呼んでいますが、これはある意味、過去の何かにしがみついて離れようとしていると同時に、そこから抜け出そうとしているからです。私は前進したいし、もう少しテストステロンがあることをしたいんだ。このアルバムを作るか、ハーレーダビッドソンを買うか、そのどちらかだった。どっちが安全かなんてわからない。」そして「ジェフ・ベックやジョン・マクラフリンのやってる事はうまく行ってると思うし、それは自分のやりたい事でもあるので、しばらくこういうエレキのインストをやる」と言ってますね。
これには「マジなの?」と驚いたもんです。とにかく彼が「中年の危機」なんてワードを出すくらい、自分の今までの音楽とは全く違う事をやりたかったのだと言う事はわかったし、いろんなやり方を模索しているのはわかった。それは後述の「ドミニクのコメント」にある彼のコメントからも感じられます。
しかし、当時の彼のインタビューを見ていると、本気なのか冗談なのかわからないものもありました。彼はフランスに住んでいますが、ドイツを拠点にしているため、ドイツのメディアでは『そこまではっきり言って大丈夫なのか?』と心配になるような話もありました。
ドミニクは非常に率直で、メディアに対してもファンに対しても、必要以上に自分を良く見せようとしない、時に「正直すぎる」人物だと私は思っています。彼は自分が思っている事を素直に話す傾向があると思います。
個人的には、その「正直さ」が彼をとても「信頼できる人間」にしていると感じるのだが、どう思いますか?
いくつか例を挙げてみます;
「エレキギターを始めたのは、私の中にある最後の青春のかけらを恋しがっているからだ。このアルバムの後、私がナイロン弦の王様になったという話を突きつけられないことを願っている。とにかく、今の私の人生には混乱が多い。(中略)スティングとピーター・ガブリエルが、これまでの私の音楽人生のすべてを実質的に占めていたからです。 彼らのサイドマンとして、そして彼らのポップとロックの概念の文脈において、私はいつも自分自身を偽物だと思っていました。 私は、ロックスターでなければならないのなら、ロックスターですが、いつもインチキ者です。とりあえず、私は演技の仕方はよく知っていますが、これまでは本格的な音楽にしか興味がありませんでした。」
エレキギターで新しいアルバムをレコーディングしたとき、少なくとも少しは若かったと感じましたか?という質問には、
「ええ、もちろん。ハーレーを買う必要はなかった。バイクの轟音よりもエレキギターの方が、自分の年齢的なフラストレーションをたくさん表現できたからだ。真面目に言うと、次のアルバムではもっとヘヴィな領域に踏み込みたいんだ。スティングやガブリエルのキャリアが若い頃の明確な恐怖の上に築かれたのとは対照的に、私は新境地を切り開くことになるだろう。次はメタルの世界に入りたいんだ。」と答えています。まぁ、そして実際に「メタル」ほどではないですが、やはりエレキ・ギターを全面に出した「5Th House」を2年後にリリースします・・・。
ドミニクは当時このような事を語っていました。
「スティングのような多くの偉大なアーティストと仕事をすることの報酬のひとつは、セールスを気にすることなく、今回のようなレコードを作ることができるということだ。マーケティングや他の誰かの期待に答える必要がない。だから、本当に好きなことをやっているだけなんだ。」
確かに彼は恵まれた「環境」ではあったのだと思います。しかし、このアルバムの制作に関する以下のドミニクのコメントを読むと、私の個人的な感覚では、この時期は彼自身の音楽において、かなり試行錯誤し、「何かを得る」ために少し苦労していた時期だったように思う。
その苦労していたところはやはり「作曲」の部分だったのかな、と思います。
でもこの作品と次の『5th House』でエレキギターのアルバムを作った事で、彼としてはもう思い残す事は無くなったというか、これからはやはり自分はアコースティックな音楽に重点を置いていこうと明確に思えたのかな?という気もしました。
使用ギターについて
使用ギターですが、このアルバムでは彼は1972年製のレス・ポールを使用しているはずです。実際当時のツアーやインタビュー時、このアルバムの写真でも持っているのはレス・ポールです。彼はレス・ポールは「ロックな気分の時に持ちたいギターだ」と話していました。しかし今はもうレスポールを持つ姿をずっと見ていません。ただ、エレキでもこれだけの演奏ができる人なので少し勿体無い気もしますね。普段今では彼のECM作品をずっと聴いていて、彼はアコースティックを追求する人だと理解している私でさえ、彼のエレキ・ギターの音はとても美しいから彼のあの音を無性に聴きたくなることがあります。
ドミニクは本当に非クラシック音楽の世界にいるミュージシャンとしては、本当に美しい音を追求し続けている人です。ただ、それは私は彼がやはりクラシックを学んでいた事と、彼の普段のメインはアコースティックギターだという事と関係していると思います。どう言ってもアコースティック楽器をやっている方が音に対する感覚は敏感になると思うので、恐らくエレキギターしかやらない人とは違うと思います。
アコースティックのイメージの強いドミニクですが、彼もジミ・ヘンドリックスやジミー・ペイジ、ジェフ・ベック、そしてグレイトフル・デッドのジェリー・ガルシアが大好きだったギター少年でした。そしてStingの所に来て最初の『The Soul Cages』のアルバムやツアーでエレクトリック・ギタリストとして全世界に衝撃を与えました。彼のエレキギタリストとしての演奏をあまり聴いたことがない人がいるなら、『The Soul Cages』や『Ten Summoner’s Tales』の頃のライブを見て欲しいと思います。彼は約30年前の当時から彼にしか出せない音を持っていた人です。実に色彩感に溢れ、キラキラした様々なトーンを聴くことができます。スティングとの動画は「Videos with Sting」で紹介していきます。
曲について
このアルバムの収録曲はそれまでの作品以上にかなり音楽的にバラエティに富んでいます。ロック、JAZZ、シャンソン、ボサ・ノヴァにフュージョン、変拍子も多用されているのでプログレッシブ・ロックの印象の曲もあります。この作品でドミニクが一番望んでいたことは「自分の演奏に注目してもらう事」ではなく、「曲に注意を向けてもらいたい」という事です。これは下のドミニクのコメントを読んでいただければわかります。「曲が王様でなければいけない」と言っています。私は彼がこのことをハッキリと意識した点でこの作品はターニングポイントになっていると思います。この大変大きな気づきは今の彼の音楽において大きな影響があったと思います。
この作品は曲を書き始めてからレコーディングまで驚くほどのスピードで完成されています。そして演奏の90%はほぼファーストテイクだったと語っています。つまりドミニクは恐らくなるべく曲の発想を得た時の最初のインスピレーションをできるだけ損なわないようにしたかったんだと思います。実際に最初の『First Touch』の時のような作曲の感覚を取り戻したい、という趣旨の発言をしています。
また、ドミニクはこのレコーディングにあたり、結構な無茶な要求をメンバーにしています。他の奏者に対し、「なるべく個性を出さないでくれ。曲をその曲のあるがままの形で演奏してほしい」と。これは参加ミュージシャンは面食らったでしょうね。でもこれも結局は曲に対する自分のインスピレーションを一番強く打ち出したい、という意図だったと思います。
この作品は全編ダークなトーンの中にも、やはり私は本当に彼の音や音楽に「色彩」を感じます。1曲目の「Solent」から彼独特のコード使い、抒情的なメロディセンスを感じます。抒情的な1曲目の後にはゴリッゴリのヘヴィーな「W3」が来ます。
この「W3」に関してはインタビュアーの「新曲“W3”ではストリングスを叩きつけようとしていますね?」という質問にこう答えています。
「すごいですよね? ヘヴィなリフで、曲の文脈の中でのコントラストがとても気に入りました。 私たちは典型的なフュージョンのソロが主導的な役割を果たしているフュージョンの風景の中にいて、突然この異物ようなリフにぶつかります。 突然、フュージョンはある種の風刺画になってしまいますが、私は音楽的なユーモアが好きなので、これがとても気に入っている。 最後に私は2つの音からなるオスティナート(繰り返しの事)を演奏しますが、これは次のこと以外は何も言わないはずです。「全部くたばれ、もう今は本当に弾けない。だけど誰が気にする?」
そしてその後には泣きたくなるほど圧倒的に美しいメロディーとトーンの「Still」が来ます。そしてこの後にはこれまでの彼の作品にはあまり無かった曲調の「Gut Feeling」と「Ripped Nylon」(裂けたナイロン)が来ます。これらの曲は今でもライブで演奏されることがあります。是非、の動画やリンク先のYouTubeの動画を見て欲しいですね。めちゃくちゃカッコいいです。
「Gut Feeling」はアメリカのピアニスト、ピーター・ケイターとのデュオアルバム『In A Dream』(2008)制作時に書かれた曲ですが、それとは全く印象が変わっています。
で、その後の「Racine」。これはドミニクが11歳まで過ごしたアルゼンチンを離れ、アメリカに渡って住んだ街の名前です。彼のお父さんはジョンソン・ワックス社(今のSCジョンソン)の社員で、アメリカ・ウィスコンシン州のラシーンに本社1があります。ですからその転勤に伴って彼はアメリカに移住します。年齢的にも多感な時期に初めて過ごしたアメリカの街の彼の記憶が想像できるような作品です。なにか少し切なくて甘酸っぱいけど美しい情景を感じます。
「Chanson I」,「Chanson Ⅱ」これはタイトル通りシャンソンからヒントを得た曲でしょう。ただ「Ⅰ」の方はこれは個人的にはシャンソンの印象はあまり受けない曲なので、どういうイメージで作ったのか気になります。
「Ⅱ」の方はシャンソンでもあり、ボサ・ノヴァ風でもあり、不思議な感覚を受けます。ドミニクはシャンソンは好きだと言ってました。彼はもう長くフランスに住んでいますが「音楽的にもイタリアよりもフランスのものが好きなんだ」と言っています。ドミニクの音楽にとって「色彩感」というのはキーワードの一つです。確かにフランスの方がイタリアよりも色彩感をより感じる音楽であると思います。フランスという国は音楽だけでなく独特の敏感な色彩感覚がある国だと私も思います。日本にも伝統的な色と美しい「色合わせ」が存在しますが、勿論それはフランスにも存在します。彼らの色の感覚はとても繊細です。私はフランスには3週間ほど滞在した事があるだけですが、それでもそれは感じました。だから彼にはとても合っている国なんだと思います。
「Marignane」はフランス南部のマルセイユにある彼の家の近くの空港の名前だそうです。「それ以外に理由はないから、かなりくだらないタイトルだけど、僕はこの人たちと同じように空港で多くの時間を過ごすから、それがつながりなんだ。」なんて話してましたね。ドミニクは本当に世界各地に行っている人という事もありますが、色んな場所の名前の曲がありますよね、今度数えてみようかな(笑)次のアルバム『5th House』には「Tokyo」という曲も登場します。
Bonus Track
実はこの作品はアナログ2枚組も発売されています。そこにはボーナストラックが3曲入っています。これは今、配信の方で聴く事が出来ます。


この動画を YouTube で視聴


この動画を YouTube で視聴
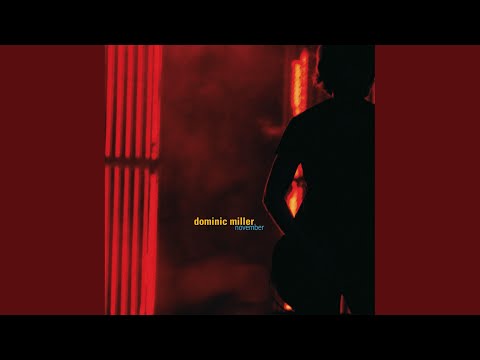
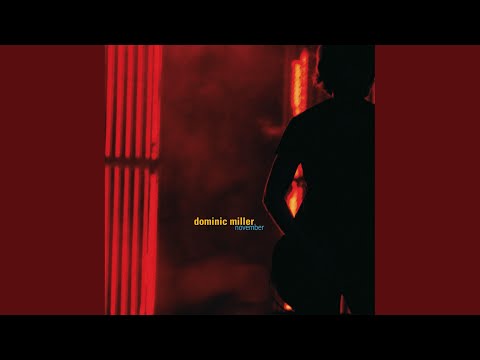
この動画を YouTube で視聴
A1. 「November Reprise」はヤーロン・ヘルマンのパイプオルガンのような音が完全に教会を思い起こさせる厳粛な感じの曲です。アナログではこの曲の後に、1曲目の「Solent」が来ますので、通して聞くとこのアルバムの最初の印象がかなり変わりそうです。
C1.「Bachiana No.5」。これは彼が敬愛するブラジルの大作曲家、ヘイター・ヴィラ・ロボスの曲で、本当は前作の「Forth Wall」に収録する予定だった曲です。しかし結局「Forth Wall」の内容には合わなかったため、収録を見送っています。このヴィラ・ロボスの作品は組曲で、原題は『ブラジル風バッハ』(Bachiana Brasileiras)です。「現代版(またはブラジル版)のブランデンブルク協奏曲」と言われる有名な作品です。その中でも「No.5」は重なるメロディのポリフォニーが大変美しく、最も有名な曲です。ドミニクの演奏も大変に美しいです。
C3. 「Chanson II Reprise」ですが、これは「Chanson II 」のエレキギター・ヴァージョンですね。曲調のせいもあるかもしれませんが、めっちゃラリー・カールトンっぽい感じですね。ドミニクはおそらくラリー・カールトンにはかなり影響を受けていると思います。
ジュリア・フォーダム
最後に追記です。このアルバムの「Still」と「Chanson Ⅱ」はなんと、ジュリア・フォーダムの歌がついたヴァージョンが存在するんです!これは私も見つけた時は驚きました。2曲とも彼女のシングルとしてリリースされています。
ドミニクは1989年リリースのジュリアの名盤『Porcelain』に参加していて、ギターを弾いているだけではなく、自宅のスタジオを制作に提供したりドラムのプログラミング等、かなり貢献をしています。そして、実はドミニクが日本に来たのは、スティングの『The Soul Cages Tour』が初めてではなく、先に彼女のコンサートで来日しています。まだ私はその頃ドミニクの事は知りませんでしたが。彼女のこのアルバムの1曲目の「Lock And Key」から「これはドミニク・ミラーが弾いている!」とすぐにわかる特徴的な音と演奏をしています。当時、まだドミニクは30歳前です。しかしこの頃からこんなふうに聞いてすぐに彼だとわかる音と演奏だったんだと改めて驚きます。


この動画を YouTube で視聴
ちょっと余談になりますが、この曲でのドミニクについて、ジュリアが面白い話をしていました。
「ギターのドミニク・ミラーには、私が何度もギターを弾くのを止めようとしても、頑なに弾かせようとするその頑固さに何度も驚かされたものだわ!」
このドミニクの「頑なに弾かせようとする頑固さ」はなんだか私も見た記憶があります。それはスティングの1994年のドキュメンタリーの映像です。ここでドミニクはスティングのNYの自宅でスティングと一緒に「Venezuelan waltz」を弾いているんですけど、スティングが間違えて演奏をやめても間髪入れずに繰り返し弾かせているのがとても面白くて強く印象に残っています。その動画の一部はYouTubeにあるので、よかったら一度見てください。
話が脱線しましたが、ジュリアの曲の話に戻ります。「Still」が「Red Silk Dress」、「Chanson Ⅱ」が「You Left Me For Dead」というタイトルになっています。
これ、皆さん聞いていかがですか?私、ジュリアも好きですよ?だけど結構歌入れるのは無理ありませんか?最初聞いた時バリバリに違和感ありました。だいぶ慣れましたけどね。「You Left Me For Dead」はまあシャンソンベースの曲なんでそこまで違和感はないですけど。
「Red Silk Dress」は後半、ジュリアの声が多重録音されていて、それは綺麗は綺麗なんですけど、どうですかね・・・。ちょっと微妙・・・。私がこの曲はドミニクのインストヴァージョンのイメージが強すぎるのかもしれないですけどね。
それとこの2曲のジャケットのデザインもどうなんでしょうか?ジュリアの写真とドミニクの写真があまりにミスマッチだと思うんですけど。私だったらこのデザインは絶対OK出さないです!😅 余談でした。
Dominic’s Comments
早くからドミニク・ミラーのファンであった人たちには、驚きが待っている。これまで彼は、ナイロン・ギターから生み出される絶妙なアコースティック・サウンドで賞賛されてきたが、ソロ・キャリア初のエレクトロニック・アルバムで、聴衆と専門家の双方を困惑させている。最新作『November』では、エレクトリック・ギターのためのスペースがたっぷり用意されている。ミラーのロック志向の一面を示す曲もあり、時に驚くほどパワフルなサウンドを聴かせてくれる。その証拠に、文字通りのスラマー「Rippled Nylon」やファズに染まった「W3」のようなトラックがある。
この心境の変化には理由がある。2008年秋、ロンドンを本拠地とするミラーは、これまで制作されたすべてのCDをじっくりと聴き、そのほとんどが作曲的に濃密というよりも、むしろ濃密なサウンドに重点を置いていることに気づいた。彼のソロ・アルバムの中で唯一例外だったのが、デビュー・アルバムの『First Touch』だった。ミラーは回想する:「あのアルバムは、私が35歳だった1995年まで吸収してきたすべての影響を表していた。スティングとの “Ten Summoner’s Tales “ツアーから帰ってきてから作ったんだ。音楽的自伝のようなものだった。『First Touch』をレコーディングしたときに幸運にもいられた空間を再現したかった。あのプロセスで覚えているのは、自由な感覚だけだ。まるでアルバムが自分で書いているような、私に命令されているような感じだった。つまり、私はただ点と点をつないだだけなのだ。それが “神からの贈り物 “だと言うほど大胆ではないが、当時はそんな感じだった。」
ドミニク・ミラーにとって、『November』は『First Touch』を超えた、書き直された自伝のようなものです。これらの「音楽に込められた思い出」を捉えるために、まるでこれまでスタジオに入ったことがないかのように、彼はゼロから始めました。
「家を掃除して、その 4 枚のアルバムを置いて再びゼロに戻りました。」 実際の制作に取り掛かる前に、才能あるギタリストは、自分が取ろうとしている方向性を本当に確信するために時間を費やしました。 彼はさまざまなアプローチを分析しましたが、最終的に軌道修正の時期が来たと判断しました。 その結果、ボーカリスト不在のバンド編成となった。 しかし、そのような楽器編成には、固有の危険性と制限もありました。
「二流のフュージョン バンドやジャズ ロック バンドのように聞こえる危険性があります。 神は禁じます! 名前は挙げませんが、私は何人かの非常に有名な楽器奏者からそのようなレコードをいくつか受け取りました。 それらのレコードは一度聴いただけでは、冬の間、私のプジョー206のフロントガラスについた霜をこすり落とすくらいしか使い道がなくなってしまった。これらのレコードの多くは、すべてではないにせよ、そのほとんどが作曲ではなく演奏が重点にある。それらの曲の作者は、平均的な脚本を持つ偉大な俳優のようなものです。私は、作曲が王様でなければならないと決心していました。」
この目標を達成するために、ミラーは関係者全員に「私に個性を与えないで、曲をあるがまま自然に演奏してください!」」と説明しました。この願いに賛同してくれるミュージシャンを見つけるのは容易ではなかった。しかし、最終的にミラーは、ドラマーのイアン・トーマス(エリック・クラプトン、シール、ポール・マッカートニー、トム・ジョーンズ)、ベーシストのマーク・キング(レベル42;スラップ・ベースの無敵の名手)、キーボードのマイク・リンダップ(同じくレベル42で知られる)というセッション・パートナーを見つけ、彼らは自分たちのエゴは最後にする事に同意した。この核となるミュージシャンに、イスラエル出身で現在はフランスに住むピネシストのヤロン・ハーマン、キーボーディストのジェイソン・レベロ(スティング)、フルート奏者のデイヴ・ヒース(フルート、ヴァイオリン、オーボエのコンサートの作曲家として有名)、サックス奏者のスタン・スルツマン(ケニー・ウィーラー、マイケル・ブレッカー、NDRビッグバンド)を加えた。彼らは全員、自分の独特の音楽的個性を後回しにして、ミラーの作品に独自のスキルを捧げた、精通したトップ・プロフェッショナルです。
このような献身的なサイドメンに支えられて、ミラーは、あらゆる種類の予想外の展開、スタイルのバリエーション、はっきりと革新的な音の組み合わせを提示するインストゥルメンタル・アルバムを作り上げた。ロック「W3」、「Ripped Nylon」、ニューエイジの瞑想「Still」、ラウンジ・ミュージック「Solent」、サウンドスケープ「Gut Feeling」、ファンク「Sharp Object」、クラシック音楽への言及「Chanson II」、ジャズ・モーメント「Marignane」が、現代インストゥルメンタル・ミュージックの独特なスタイルを形成している。
このアルバムをプロデュースしたのはドミニク・ミラーとヒュー・パジャムで、彼らはフィル・コリンズのミリオンセラー『But Seriously』(1989年)を手がけて以来、事実上切っても切れない関係にある。過去20年間、彼らは多くのプロジェクトで協力し合い、お互いを盲目的に信頼している。「ヒューは私が何を求めているかを理解してくれたので、プロデューサーに選ぶのは明らかだった」とミラーは説明する。「ヒューはキラー・サウンドを手に入れるんだ。」
実際の制作過程に関して言えば『November』はドミニク・ミラーがこれまでに制作したアルバムの中で最も「早い」作品となった。作曲にかかった時間はわずか3週間、レコーディングとミキシングはわずか2週間だった。アルバムに収録されている演奏のほぼ90%はファースト・テイクだ。「何でもかんでも操作できるプロ・ツールのような完璧なやり方から離れたかったんだ」と、ミラーはその速い作業方法と、スタジオにもっと自発性を認めるという決断を説明する。そのため、「タイミングやチューニング、アーティキュレーションに不完全な部分がある。いつもならこれらを修正するのだが、今回はありのままの演奏を生かした」。
■ Video ■


この動画を YouTube で視聴


この動画を YouTube で視聴
4曲目「Gut Feeling」のアルバムバージョンと実際の彼のバンドでの演奏を並べてみましたもう全然別の曲みたいになってます。圧倒的にライブがいい。だから皆さん、彼のライブに行きましょう!😅ドミニクはライブアルバムは殆ど聞かないし興味がありません 。「一番好きなライブアルバムは何ですか?」と聞かれ、「ディープ・パープルのメイド・イン・ジャパン。終わり。私は一般的にライブアルバムの大ファンではないので、一度もアルバムを作ったことはありません。それを体験するには、実際にライブに行かなければならないと思います。」って言ってます。まあそれは仰る通りだと思います。
このライブの演奏ですけど、ドミニク・ミラーという人のミュージシャンとしての凄さに改めて震えがきたものです。ほぼパーフェクトじゃないでしょうか。まあご本人はこれでも全然満足はされていないと思いますが。もう永遠に聴いていたくなるような、そんな音と表現の演奏です。センスの塊だし絶妙のバランス感覚がありますね。徹底的にコントロールされた表現です。本当にすごいと思います。ここまでコントロールする人は私はロックやPOPSではあまり見かけた事はないですね。私はこの演奏を聴いた時に、ドミニク・ミラーというミュージシャンに初めて「嫉妬」しました。後にも先にも、その人の才能に嫉妬したミュージシャンは彼だけです。
上の「November」という曲も、アルバムの録音ではジェフ・ベックに肩を並べられるのは彼くらいだろう、と思わせるような凄い演奏していますが、実際にライブで演奏する時はもっと抑えた表現を彼はします。でもそれがいいんですよ。彼は絶対に自分が目立つよりも全体のバランスを考えた演奏をします。ただ、それは所謂多くの「ギターヒーローを望むギターキッズ」にはウケないんだろうな、とは思います。やっぱりそういう人たちは分かりやすいテクニックの披露のようなものを好む傾向がある。だから時々、ちゃんと理解できる人には「ドミニク・ミラーは時々『犯罪的に』過小評価されてる」と言われたりするんだろうな、と思います。
まあ、別に彼自身も「ギターヒーローになろう」なんて思ってはいないだろうからどうでもいい事なんですけどね😅ファンである私もそんな評価は一切望んでない。私が望んでいるのはただドミニクの音楽を一人でも多くの人に聞いて欲しい、という事。そして個人的には「ドミニク・ミラーという音楽家がどこまで自分の音楽を追求してそれを全うしてくれるか。そしてどこまで到達してくれるかを見届けたい」という事だけです。
■ Review-1 ■
レビュー:アルゼンチン生まれのギタリスト、ドミニク・ミラーは、そのキャリアの大半において、他のアーティストのサポートにその計り知れない才能を発揮してきた。おそらく “スティングのギタリスト “として最もよく知られ、その肩書きを誇りに思っているが、ミラーのユニークなアコースティック・サウンドは、フィル・コリンズ、レベル42、プリテンダーズ、クリス・ボッティ、ザ・チーフタンズ、さらにはバックストリート・ボーイズといったアーティストの作品にも絡んでいる。常に時間と才能を要求され続けているミラーだが、ソロ活動にも時間を割いている。最新アルバム『November』は、ミラーのこれまでとは明らかに異なる一面を見せている。
ミラーは『November』で新たな領域に踏み込み、エレクトリック・ギターとの関係を新たにし、ヴォーカルを完全に排除し、派手なスタジオ機材のプラグをすべて抜いた。『November』のナンバーは数日でレコーディングされ、ミラーの音楽的旅路における現在の位置を記録している。先週のインタビューで、全曲インストゥルメンタルのアルバムを制作するという決断について尋ねたところ、ミラーはこう答えた。”間違いなく世界最高の本業のひとつである仕事をしながら、それとは正反対のインストゥルメンタル・ミュージックだけをやるというコントラストが好きなんだ”。彼の理由が何であれ、その結果が物語っている。
『November』にはギター主体のインストゥルメンタルが 11 トラック含まれています。 ミラーのバック奏者には、ドラマーのイアン・トーマス、ベーシストのマーク・キング、キーボード奏者のマイク・リンダップ、ピアニストのヤロン・ハーマン、フルート奏者のデイブ・ヒース、サックス奏者のスタン・スルツマン、キーボード奏者のジェイソン・レベロが含まれる。 多くのトラックは「ファーストテイク」レコーディングを表しており、ミラーは私に、「不完全な点はすべてそのままにしておくことが望ましい。」と語った。 「本当に分析しようと思えば、実際にはいくつかの間違いがあり、チューニングの問題やテンポの問題もあります。」と彼は言った。「ProTools 世代はすべてを台無しにしました。なぜなら、今ではすべてが完璧のようだからです。不完全さがあるからこそ、何かが美しくなります。何かを機能させるのは、完璧と不完全さのコントラストです。」
ナイロン弦のアコースティック・ギターが主役の「Solent」で始まり、1分も経たないうちにエレキ・ギターが登場する「W3」は、ハードコアでアース・ウィンド&ファイアーを彷彿とさせるファンク・グルーヴで始まる。それでもミラーは、ジャズ・フュージョンのフレイバーを加えて変化をつけ続ける。この傾向は『November』を通して続き、折衷的な個性を与えている。ダークなトーンとアティテュードが甘いサックス・ソロで際立つ「Marignane」に1票を投じたい。
ミラーは 『November 』をこう要約している: 「スティングのような多くの偉大なアーティストと仕事をすることの報酬のひとつは、セールスを気にすることなく、今回のようなレコードを作ることができるということだ。マーケティングや他の誰かの期待に答える必要がない。だから、本当に好きなことをやっているだけなんだ」。私は、彼がそうしてくれたことを嬉しく思う。Creative Loafing (Tampa)
- 完全な余談ですが、ドミニクが過ごしたアメリカのラシーンにある彼のお父さんの会社、ジョンソン・ワックス社の本社というのはあの近代建築の巨匠、フランク・ロイド・ライトが設計した有名な建築です。今でもこれは見学が可能です。ウィスコンシン州というのはライトが生まれた場所でもあり、数多くの作品を残した場所です。そしてドミニクが卒業した高校「プレーリー・ハイスクール」の建物もライトの死後を引き継いだ「タリアセン研究所」が設計しています。だから後年ドミニクが建築は「フランク・ロイド・ライトが好きだ」と語っていたのはそういう環境で育っていますから当然でしょう。そしてとても羨ましくもあります。 ↩︎
- As a complete aside, the headquarters of his father’s company, Johnson Wax, in Racine, USA, where Dominic spent time, is a famous building designed by the master of modern architecture, Frank Lloyd Wright. It is still open for tours. Wisconsin is also where Wright was born and where he left many of his works. The building of Prairie High School, from which Dominic graduated, was also designed by The Taliesin Institute, who took over after Wright’s death. So it is no surprise that Dominic said in later years that he “loved Frank Lloyd Wright” when it came to architecture, because he grew up in such an environment. And I envy him very much. ↩︎