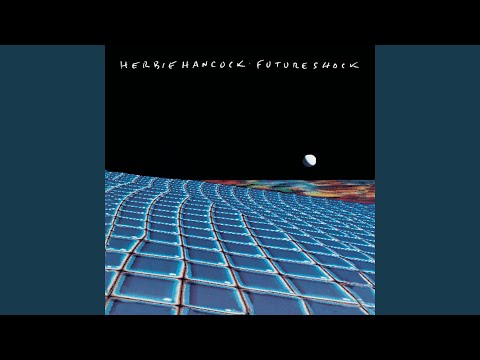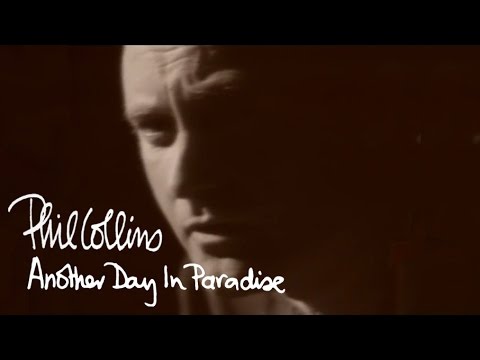Chat between Dominic and Andy Edwards Part-2
ドミニクが、2025年9月26日にスティング3.0のツアーで台湾に滞在中に音楽系YouTuber のアンディ・エドワーズ(Andy Edwards)と行った対談の全文書き起こし翻訳のPart-2です。会話の内容は全く変えていませんが、前後のつながりや、内容を補足するために言葉を加えたり、意訳してありますのでご了承ください。Part-2は約22分くらいから48分までの内容になります。(Part-1はこちら)
ここで彼らが話しているのはケニー・カークランド、ブランフォード・マルサリスらがスティングの音楽にもたらしたJazzの影響について。また、スティングの曲で描かれている内容はどこから来ているのか。ドミニクが参加したフィル・コリンズのメガヒットアルバム『…But Seriously』のレコーディングについて、スティングの『Ten Summoner’s Tales』に参加したキーボーディストのデヴィッド・サンシャスの話と、あのアルバムのMVについてです。
The chat between Dominic and the musician and YouTuber Andy Edwards during the Sting 3.0 tour in Taiwan on 26 Sep. 2025 was truly fascinating. For Japanese fans, I have transcribed and translated the dialogue, this is the Part 2. Part 2 covers the content from approximately 22 to 48 minutes in.(Part 1 is here.)
Here, they chatted about the jazz influence Kenny Kirkland and Branford Marsalis brought to Sting's music, and where the inspiration for Sting's songs comes from, the recording of Phil Collins' album “…But Seriously”, on which Dominic participated. Additionally, it concerns keyboardist David Sancious, who participated in Sting's album “Ten Summoner's Tales”, and the music video for that album. Also,For those in English-speakers who understand the content, as numerous musicians—primarily from the prog rock scene—appear, I have endeavoured to include video clips alongside supplementary commentary.
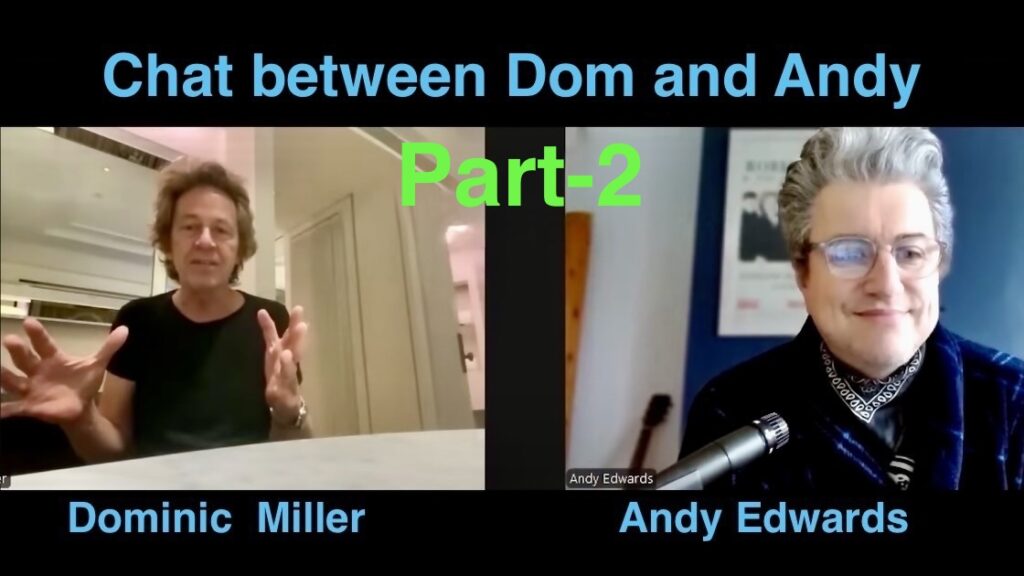
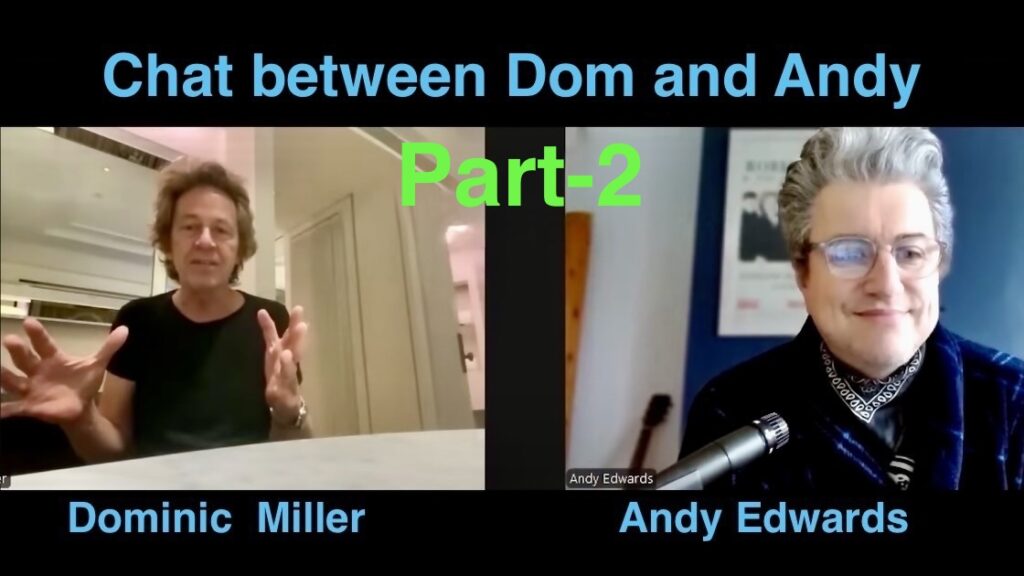
このPart-2の記事は約22分から48分までの内容です。
ケニー・カークランドの影響
(22:24)
Andy(以下A):あなたはずっと長い間スティングのバンドに在籍していますよね。 だからぜひ、このバンドにおける「ジャズの影響」について話を聞きたいんです。 というのも、これまで本当に多彩なプレイヤーが参加してきましたから。
僕が最初に思い浮かべたのは、最初にあなたに会ったときにはあまりその話をできなかったんですが、もっと詳しく聞けばよかったと思ったのは、20世紀後半の最も偉大なジャズピアニストの一人、ケニー・カークランドのことでした。残念ながらもうこの世にはいませんが、共演するのに本当に素晴らしいプレイヤーでした。彼は「純粋なジャズ・プレイヤー」でしょう?でも、スティングのバンドで長く演奏していましたよね?彼はバンドにどんなものをもたらしていたのでしょうか?
Dominic(以下DM):そう、ケニーは純粋なジャズ・プレイヤーでした。彼がスティングのバンドに最初に参加したのは、僕が『ニンジャ・タートルズのアルバム』と呼んでいる作品のときなんです。(筆者注:1985年のアルバム『ブルータートルの夢』のこと。Part-1でドミニクがケニーら、ジャズ・ミュージシャンを「ニンジャ・ミュージシャン」と呼んでおり、アメコミ映画の『ミュータント・ニンジャ・タートルズ』をかけている。)
それが最初で、彼はその後しばらくの間スティングと一緒に活動を続け、その後一度バンドを離れて、僕が参加したとき(筆者注:1991年のアルバム『The Soul Cages』)にまた戻ってきたんです。実際、ケニーについて言うと、あなたの言う通り、彼はバンドに本当に大きな影響を与えました。だって僕がこのバンドに入ったとき、特に前任者のようなギタリストがいなかったんだ。つまり、「このバンドでギターをどう弾けばいいのか」という手がかりをくれる、師とあおげるような存在がいなかったんだよ。
A:だって、それまではスティング自身がギターを弾いていたんですよね?
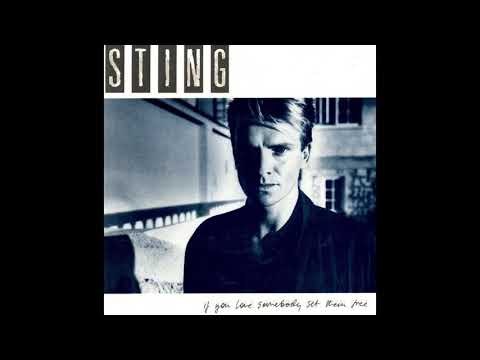
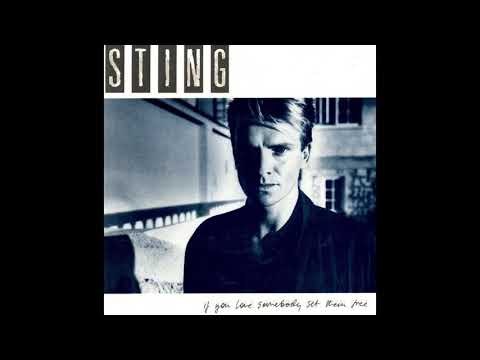
この動画を YouTube で視聴
1985年の『ブルータートルの夢』。このアルバムには、ケニー・カークランド、ブランフォード・マルサリス以外にはオマー・ハキム、ダリル・ジョーンズ(マイルス・デイヴィス、ローリング・ストーンズ)などが参加している。


この動画を YouTube で視聴
1988年のNothing Like The Sun Tour。ケニー・カークランド、ブランフォード・マルサリス以外に、次に出てくるギタリストのジェフリー・リー・キャンベルもいた。
DM:ええ、スティング自身がギターを弾いていたんです。それから、ジェフリー・リー・キャンベルというとても上手いギタリストがいたんですが、でも彼の役割はそこまで目立つギターパートというわけではなかったんです。どちらかというと、セカンド・ギター、あるいはスティングと2人でリズム・ギターを弾いていたような感じでした。だから僕はずっと、「自分の道しるべになるのは誰なんだろう?」と思ってたんだ。そして僕はケニーとブランフォード・マルサリスこそが、スティングの「音楽の方言」を誰よりも理解している2人だと感じたんだ。それはまさに「方言」というか「アクセント」のようなもので、彼らには独特の和声的なアクセントがあったので、僕はそれを手本にしたんだ。
ケニーがコードをどうヴォイシングするか、あのメロディに対してどのようにヴォイシングするか——。そこが本当に鍵だったんだ。つまり、伝統的なジャズ・コードをそのまま使うのではなくて、重要なのはどの音を省くかなんだ。
これについてはいつまででも話せるけど(笑)繰り返しになるけど、それらのコードは決してすごく「分厚い」コードではないんだ。でも、響きとしてはとても豊かに聴こえるんですよ。本当に太く豊かに聞こえるんだ。(筆者注:この話はPart-1で詳しく語られている。)
ブランフォードと「Englishman in New York」
(25:23)
A:チャンネルを見ているみんな、ちょっと注目してくれ。それは本当に興味深いね。僕はケニーの演奏で、その点には気づいていなかった。ブランフォードがスティングのバンドに加わったとき、もちろん彼はいくつかのソロを担当していたけど、そのパート自体がまるでクラシックのオーボエやクラリネットのように聴こえたんだ。もちろんブランフォードもウィントン・マルサリスも、どちらもクラシックの訓練を受けていて、そういう演奏ができたよね。 そして僕は、ブランフォードの演奏にはある部分でどこか「英国的な響き」があるように感じたんだよね。そう考えると、スティングのバンドの中には確かにクラシック音楽の影響があるんだね。 本当に面白い話だよ。
DM:そう、まさにそんな感じ。実際には、僕たちが想像しているよりもずっと少ない音数しか弾いていなかったんだ。だからこそ、逆にサウンドが大きく聴こえるんだよ。すごく巧みで、ほとんどクラシックの和音のようで、まるでショパンみたいなコード進行なんだ。ケニーのコードには、クラシック音楽の影響がすごく色濃く出てるんだよ。
A:そうだね。
DM:ああ、まさにその通りだね。でも面白いのは、君が「イギリス的な側面」について話していたけど、彼はまず何よりも第一に。「歌詞の物語性(ナラティブ)」と、スティングの声の響き(声質・音色)をよく聴いていた。それがまさに彼の凄さを示す素晴らしい例だ。そして、それに寄り添うように、まるでボーカルのまわりを踊るように音を重ねて補っていたんだ。本当に賢いやり方だったよ。彼のように音を埋めるように演奏するのではなく、大抵のサックス奏者は歌手と共演するときは歌手が歌っている間は吹かない。でもブランフォードのやり方は、それよりずっと知的で、音楽的にも洗練されていた。
僕自身もそのアプローチをやろうとしているんだ。ときにはスティングとユニゾン(同じ旋律)で演奏したり、あるいは同時に別の旋律を弾いたりすることもある。問題は、「スティングの演奏に合わせてどうやって自分のメロディを作るのか?」「今、自分たちはどんなモード(音階)でやっているのか?」という事なんだ。
正直に言うと、僕はジャズ理論の専門家じゃないし、モードの名前なんてほとんど知らない。僕はただ感じるままに弾いている。スティングの事じゃないけど(笑)、ミクソリディアンとかフリジアンとかリディアンとか、そういう理屈は全部どうでもいいんだ。スティングの音楽は基本的にすべてモーダル(旋法に基づいたもの)だから、そういう理屈は理論家が分析すればばいいんだよ。
A:モード(旋法)って、結局のところ「音の響き」そのものですよね?
つまり、サウンドとしての感覚であって、誰もが自分なりのやり方でそこにたどり着くものだと思うんです。
(27:15)
DM:そうそう。でもね、ブランフォードはいつも、スティングが歌っているスケールに対して最適なスケールを選ぶんだ。そして同時に、ケニーはぴったり合うコード・ヴォイシングを見つけ出していた。だから、彼ら2人が、このスティングのバンドで自分がどうアプローチするべきか?という問いに対して、僕にインスピレーションを与えてくれたんだ。
それに、アンディ(・サマーズ)以外に聴けるギタリストがいなかったからね。アンディからは「空間の使い方」と「サスペンス(解決しない緊張感)」を学んだ。 つまり、「サスペンデッド・コード(保留された和音)をあえて解決しない」ということ。 僕はこの「解決しない和音」のアイデアが大好きなんだ。アンディはよくそういう事をやっていた。それによってその緊張感が持続するんだ。だからそれがこの和音の名前の由来になっているんだ。(筆者注:この話もPart-1で詳しく語られている)
そうだな、これは本当に面白い話だ。僕のアプローチに影響を与えたロックやフュージョンのギタリストは他にもいて、もちろんジョン・マクラフリンもその一人だ。前にも話したから繰り返しになっちゃうけど、マクラフリンのヴォイシングは、僕がギタリストとして身につけた表現の中でも非常に大きな部分を占めているんだ。彼のああいうアルペジオのパターンや、ピアノっぽいコード進行、そういうアプローチは僕の演奏の核になっているんだ。正直に言うと、かなり「盗ませてもらった」よ(笑)
(筆者注:これが後に「Shape of My Heart」の作曲に繋がる事になる。ドミニクはショパンの楽曲にある6度の和音を、マクラフリン的な感じでアルペジオのシーケンスなどにして、自分のギターの練習用に作成して弾いていた。それを聞いて、スティングがちゃんと曲にしようと提案した。「Shape of My Heart」に関してドミニク自身による詳しい話はこちら。)
A:今、君の話を聞いて、初めて気づいたんだけど、「Englishman in New York」のオリジナル録音を聴くと、あの「Englishman(イギリス人)」というのはブランフォード(・マルサリス)のことだね。あのサックスの音色だ。あの曲のイギリス人が彼ならば、彼はそのサックスの音でまさに「ニューヨークのイギリス人」を表現しているんだ。
「ベイカー・ストリート」のように、サックスが単にフック(印象的な一節)を吹いて、また出番を待つだけの演奏ではない。本当に興味深い。


この動画を YouTube で視聴
ジェリー・ラファティーの1978年の曲『Baker Street(霧のベイカー街)』。イントロのアルト・サックスのソロが印象的で、そのインパクトとキャッチーさで有名になった。間奏でまたイントロのフレーズが繰り返されるが、基本的に歌とサックスは共存しない。
DM:そう、あれは単なる「クールなニューヨーク的なサックス・ソロ」じゃないんだ。君が言うように、まさに「イギリス人」そのものだ。彼のあの「Englishman in New York」の演奏はかなり「イギリス的」なんだよ。あの演奏はとても魅力的でユーモアもある。
そしてスティングの音楽について多くの人が誤解しているのは、その多くが皮肉や冗談(tongue-in-cheek)に満ちているということだ。あれは彼自身の自伝的な歌ではなく、彼はキャラクターを創り出しているんだ。彼は確かに音楽を、そのキャラクターが存在する演劇のシナリオや劇中の場面の情景を表現するために作っているんだ。だから、「僕と彼女の話」だとか「僕の経験」みたいなことじゃない。むしろ「身の上話なんてどうでもいいだろ?」って感じさ。スティングはそれをわかっているんだよ。
スティングは自分の個人的な経験やそういうすべての曲から距離を置いている。 それらの大部分は彼自身や彼の経験についての事じゃない。本当に違うんだ。なぜなら彼はたくさん本を読み、演劇に興味を持っているんだ。そして演劇や、読む本の中の登場人物、詩などに興味を持っている。だからそれ(曲)は彼自身のことではない。そして私は、それは本当に賢いことだと思う。それによって僕たちは、自分達がしていることにあまり責任を感じなくてもいい。だから僕は彼と一緒に演奏しているとき、まるで劇団にいるように楽しく感じる。そう、まるで劇団の一員になった気分で、これはある場面で、僕たちはここでこのシーンを作り上げる必要がある——、という感じだよ。じゃあ、この役を特に3つの楽器(トリオ)でどうやって演じるのか?そう、いろいろできるんだよ。それはまるで演技の上手い小さな劇団のようなんだ。
スティングは曲で「自分の事」を語っていない
(30:36)
A:僕はこう思うんだ。たとえばケイト・ブッシュのような人を考えてみてほしい。彼女もまた、イギリス史上最も偉大なソングライターの一人だ。彼女には本当に素晴らしい想像力がある。彼女は母親の胎内にいる赤ん坊であることもあれば、『嵐が丘』のキャシーだったり、あるいは幽霊であったりする。どれもすごいよね。だけど僕たちは本当の彼女を実際には見ることができない。なぜなら彼女が外に出る(=公に姿を見せる)ときには、彼女はその背後にあのすべての仕掛けを持っていたい(必要としている)からなんだ。
でも僕は、もしそういった曲を(スティング3.0のような)「パワー・トリオ」のような編成で演奏したらどんな風になるだろう?とか、それをもっとシンプルにそぎ落としても成立するのかどうか?って考えるんだ。 それは本当に興味深いと思う。なぜなら、これは基本的に失われた芸術ではなく――「消えかけている芸術」だからだよ。
こういう考え方をするミュージシャン、つまり曲のために演奏できて、即興もできて、曲が自然に乗るようにフラットでダイナミクスのない演奏もできる。 (筆者注:この重要性もPart-1で語られている。)さらに、新しいことを引き起こすための一種の触媒のようにもなれる。そういういうすべての要素を持っているんだ。でも今ではインターネットが音楽性を単なる技術とスピードに貶めてしまった・・・。そして皆が注目しているのはそればかりだ。 だけど、スティングやケイト・ブッシュのようなミュージシャンが持っている要素は、それよりずっと難しくて、基本的に経験――大きなステージで、大観衆の前で曲を届ける膨大な経験を必要とする。だってそれこそが全ての決め手だよね?
僕の生徒たちはよくこう聞いてきたよ。「どうしたら上達できるんでしょうか?」って。 それで僕は言ったんだ。「たとえば誰かが君を1年間スタジアム・ツアーに雇ったとしたら、終わるころには確実に上手くなってるよ。だってそうせざるを得ないからね。」と。つまり、大観衆に伝える方法を学ぶことになるんだ。 そして君はもうそれに慣れてるんだ。目を閉じてもできるくらいだろうけど、どうやって観客に伝えるのか?それは全てのコード、全てのストローク、全てのソロに立ち姿だ。それがすべてなんだ。 なぜなら僕は君がスティングのバンドに入った頃を思い出すんだ。君はちょっとロックンロールっぽい「スワッガー(威風、ノリ)」があったんだ。それまでのスティングのバンドにはなかった要素だ。君は脚を少し広げて立って、まるで昔のキース・リチャーズみたいな仕草をしてたよね。
意外なつながり
(32:39)
DM:うん、僕は元々そういうロックっぽい文化の中で育ったんだ。スティングはもう少しロック寄りのアプローチを望んでいたけどね。 でも、実際に一緒に演奏を始めるまでは、僕があらゆる音楽に夢中だったことには気づいてなかったと思う。俺はいわば色んな音楽を知ってるオタク系のミュージシャンなんだよ。というのも、当時はセッションの仕事をたくさんやっていたから、いわゆるヘッドハンティングをされたような感じだった。 そのころ周りにいたギタリストの中では、おそらく僕が一番彼のバンドに加わるのにふさわしかったんだと思う。フィル・コリンズと一緒にやったこととか、キング・スワンプ (King Swamp)というバンドやワールド・パーティ (World Party)にいたこともあって、どちらかというとロック寄りだったしね。だから彼はそういう方向に進みたがってたけど、実際に演奏してみて初めて、僕がラテン音楽やジャズ、ファンク、さらにはプログレッシブ・ロックにもハマっていることに気づいたんだ。たとえば、僕はゴング(Gong)にもハマってたし、サイケっぽいトリッピーな演奏もできた。ディレイやエコープレックスなんかを使って、マジでトリッピーでサイケなギターや、そういう感じのやつが弾けたんだよ。
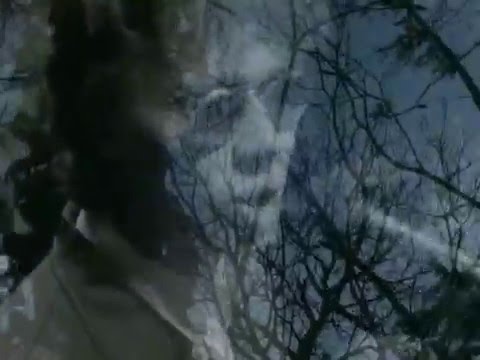
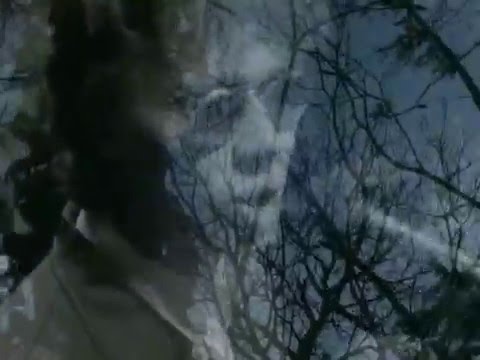
この動画を YouTube で視聴
カール・ウォリンジャー率いるWorld Partyの1作目『Private Revolution』(1987年)からのMVで、若きドミニクもしっかり写っている。2:30あたりでは変顔も披露。アルバムクレジットにドミニクの名前があるのは3作目『Bang!』(1993年)だけだが、その頃までツアーなどで関わっていたようだ。1作目はカールが色々な名前で全て自分で録音したようだ。
マルチ・プレイヤーのカールからの影響は大きく、ドミニクのアルバム『First Touch』の20周年記念盤にはカールへの謝辞が書かれており、2024年に彼がが亡くなった時に、ドミニクはこのPVを引用して追悼コメントを出した。
A:ゴングがなければスティングも存在しなかった(笑)
(14:21)
DM:ほら、つながりがあるんだよね。僕はそれに気づいてなかったけど、実はちょっとしたつながりがあるんだ。というのも、ゴングにはベースプレイヤーがいたんだ。
A:フランス人のマイク・ハウレット。さっきその冗談を言ったのはそのせいなんだよ。
そう、ポリスが結成されたのは、アンディ・サマーズがプログレ界と少しつながりがあって、ゴングのマイク・ハウレットと一緒にギグをやることになったのがきっかけなんだ。(筆者注:ゴングを脱退した後、ハウレットは短命であったスティング、スチュワート・コープランド、アンディ・サマーズからなるバンド、ストロンチウム90を結成した。
)それで、彼(ハウレット)はケヴィン・エアーズと一緒に演奏していたこともあって、それがきっかけで・・・
DM:それだ、それそれ。
A:それで彼らは、カーヴド・エアのスチュワート・コープランドを呼んだんだ。
でもね、もうひとつ面白いのは、たぶん誰も気づいていないもうひとつのつながりだけど、実はゴングがビル・ラズウェルを世に出すきっかけにもなったんだよ。
DM:へえ、ほんとに?


この動画を YouTube で視聴
ポリスの「前身」であるストロンチウム90。Gongのマイク・ハウレットとザ・ポリスのメンバーがいる。音楽的にも既にザ・ポリスの片鱗がある。
A:そうそう。そのあとデヴィッド・アレンはニューヨークに渡って、「ニューヨーク・ゴング」というバンドを結成したんだ。そのバンドにはビル・ラズウェルとマイケル・バインホーンが参加していた。それからビル・ラズウェルは「Rockit」をやって、(筆者注:下の動画を参照のこと。)あの手のヒップホップ系の流れもそこから生まれたんだよ。
DM:知らなかったよ。
A:マイケル・バインホーンはそのあとサウンドガーデンやレッド・ホット・チリ・ペッパーズのプロデュースを手掛けて、史上最も偉大なロック・プロデューサーのひとりになったんだ。つまり、ゴングは現代音楽シーンに多大な影響を及ぼしたってことだね。本当に興味深いよ。
(34:55)
DM:僕はスティーヴ・ヒレッジのギター演奏が大好きなんだ。初めて聴いたとき、本当に感動したよ。彼の演奏が大好きだ。今何をしているのかは知らないけど、彼があのバンドで演奏しているのを何度か観たことがあって、「どうやったらギターであんな音を出せるんだ?」って思ったよ。信じられないよ。本当に大きな影響を受けた。
A:うん、あのしなやかで心地よいサウンドね。
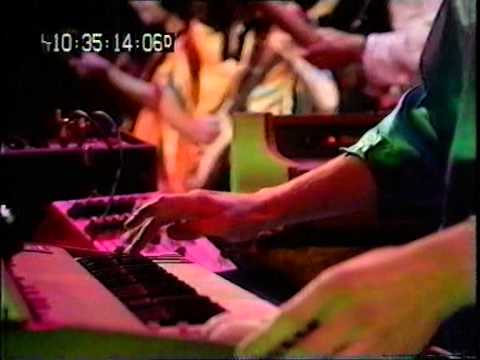
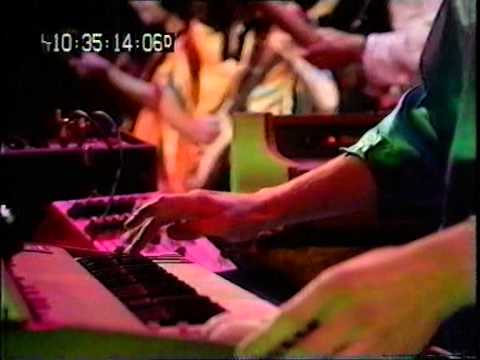
この動画を YouTube で視聴
スティーブ・ヒレッジ。ドミニクが「好きだ」ってのは凄くわかる気がします。イントロはちょっと現代音楽風だったりするけど、途中からトッド・ラングレン的な感じになったり、すっごいアグレッシブなプログレだったり。なんかギターもひらひら弾いてる感じが独特です(笑)音もとても特徴的。割と最近の演奏も、おお!?っていう感じの個性的ないい音してました。
フィル・コリンズとのレコーディング
(35:16) A:そうだ、フィル・コリンズとのセッションについて少し教えてよ。かなりいろいろな曲で演奏していたと思うんだ。しかも、「あの曲を代表するパート」を作ったのも君だろ? 「曲を代表するパート」って面白い概念だよね。でも、それがきっかけで、スティングのギグの仕事をゲットできたと思う?
DM:ああ、完全にそうだよ。間違いなくフィル・コリンズとのセッション、特に「Another Day in Paradise」での演奏が、まるで「王国への鍵」を与えてくれたようなものだった。 それで突然、自分が「新入り」扱いになったけど、実際にはそのときまでにもう15年くらい演奏していたから、まったくの新人というわけではなかったんだ。ただ、あのレベルではまだ経験がなかったというだけで。
だから、あれは本当に僕の状況を一変させる出来事だった。 そのスタジオに行ったときのことを覚えている。もちろん、僕はもともとBrand Xのファンだったんだ。唯一といっていいほど、一番「スターに会った気分」になった瞬間だったんだ。何よりも胸がときめいたのは、彼らの『Moroccan Roll』(筆者注:「モロッカン・ロール」。Brand X の1977年のアルバム)とライブアルバムを聴いた時だ。あの時思ったんだ。「なんてこった、これはジェネシスのドラマーでも、『In the Air Tonight』の人でもなく、Brand Xのドラマーなんだ!」って。僕の頭にあったのは、あの大きなヒゲの、ちょっとクレイジーなドラマーで、トリッピーで、プログレっぽいジャズ、──ウェザー・リポートみたいな感じのイギリスのバンドをやってる人、ってことだった。
それでスタジオに行ったんだよ。いや、ほんとにすごかった。何て言えばいいか分からないけど、ただそこに行ったって感じだった。僕が聞いたのはほんの少しだけで・・・。アルバムのどの段階だったのかは分からなかったけど、ヒュー・パジャムがスピーカーで流してくれた音は、キーボードと808のドラムマシンだけだった。だから僕には完全に自由裁量が与えられていたんだ。つまり、自分が「これが正しい」と思うことを何でもできたんだ。 そしてそこにいた時の数日間──僕はそのスタジオに2回行ったんだけど、自分の直感は最高に研ぎ澄まされていた。


この動画を YouTube で視聴
ブランドX・・・正直に言うと、流石に年代的に私はあまりよく知らなかった。私がフィル・コリンズを最初に知ったのは、洋楽を聴き始めた頃である1981年にリリースされたジェネシスの『Abacab(アバカブ)』でした。まず、あれだけ歌って叩くドラマーはなかなかいないし、しかも左利き!とんでもない人がいる!というのが最初の印象でしたね。その次にフィルのインパクトがすごかったのはやっぱりあの『Live Aid』だったけど、ブランドXのフィルのドラムも凄いの一言です・・・。これは個人的な見解ですが、良いドラマーには「歌心」が必要です。
(37:27)
A:でも、あの演奏を録ったとき、君は自分が「誰もが口ずさめるようなもの」を生み出したって理解してた?
DM:自分が成功するようなものを録っているとは思っていなかったけど、うまくいったな、ということは分かってたよ。その頃ちょうど、セッション・プレイヤーであるというのは、誰かを感心させようとするものではない、と気づいた時期だった。まさにひらめいた瞬間でした。あの時、「ただ曲のために正しいことをやればいいんだ」と思ったのを覚えている。アーティストのためでもなく、誰かのためでもなく・・・。そしてその姿勢は今でもずっと変わっていないよ。今でも僕が信じているのは、音楽の現場ではアーティストよりも「曲こそが王様であり、ボスである」ということなんだ。
それを理解できる人もいて、一部のアーティストやスティングのような人もそのことを理解しているんだ。 フィルは、曲を中心にして、自分の事はその背後に置くタイプなんだよ。 だから僕はこう言うしかない。「いい仕事ができた日だったよ、アンディ」って。
「Another Day in Paradise」では、ナイロン弦のギターでシンプルなアルペジオを弾くのが、ものすごく理にかなっているように思えたんだ。 それまでナイロン弦のギターはあまり使ったことがなかったんだけど、「この曲にはナイロン弦の音が必要だ」と思ったんだ。それで彼に、「その上にちょっとスペーシーなエレクトリックの音を重ねてもいいですか?」と尋ねたんだ。実はスタジオに着いたとき、僕は機材を何も持っていなかったんだ。それもよく覚えてる。ヨーロッパのどこかから直接来たから何も持ってなかったんだ。それでマイク・ラザフォードの機材を使わせてもらった。 弾いたのはスタインバーガーという、とても変わったギターで、ペグがなくてタバコを置くところもない(笑)。それとメサ・ブギーのアンプを使って、「よし、これで準備完了だ」と。 それからスペーシーな感じのエレクトリック・サウンドを少し試しに入れてみたら、彼はとても気に入ってくれたんだ。
そのとき初めて本当に打ち解けて、彼が僕をハグしてくれたんだ。すごく意気投合した感じになった。それで僕は残った。彼が「このまま残ってくれ」と言ってくれたんだ。だから僕はこのアルバムで6曲弾くことになったんだ。
(39:32)
A:つまりこういうことなんだよね。あの頃のフィル・コリンズといえば、『No Jacket Required』が3,000万枚も売れて、世界で最もビッグな存在だったわけだよ。でも彼らがスタジオに入ると、結局は「雰囲気(ヴァイブ)」と、なんというか、「じゃあ、ちょっとアイデアをジャムしてみようか」っていう、その感覚に戻るんだ。本当に信じられないすごいことだと思う。
DM:本当にそうだね。彼は素晴らしい人だったよ。僕のことをとても温かく迎えてくれた。
あの時は僕と彼とヒュー・パジャムだけだった。他には誰もいなかったんだ。
A:彼はドラマーとして本当に驚異的だよね。たとえば僕でもビル・ブラッフォードのフレーズとか、カール・パーマーのパートなら演奏できるけど、「Do They Know It’s Christmas?」のドラムを聴いてごらん。あの演奏を聴くと、「一体何をやってるんだ?」って思うよ。あれをあの通りにやるのは本当に難しいんだ。(口でビートを真似する)
DM:それは気づかなかったな。
A:あれはね、彼(フィル・コリンズ)が右手であの軽快なシャッフルをやっているからなんだ。あれ自体、ものすごく難しいんだけど、普通のドラマーならああはやらないんだよ。
それに、あのフィルが見せる「フィール」もね、僕が言っているのは、彼がやった中でも本当に基本的なことなんだけど、でも最も有名なプレイのひとつでもある。「Do They Know It’s Christmas?」の中でね、ある箇所で彼がもう一発余分に叩くところがあるんだ。
それが構造的には合わないんだけど、まさに天才的なんだ。
(41:00)
DM:あと、クリス(スティング3.0のドラマー、クリス・マースのこと)はビリー・オコーナー(筆者注:ブロンディなどで知られるドラマー)がすごく好きなんだ。彼が言うには、ビリーはフィルのお気に入りのドラマーのひとりでもあるらしい。
A:フィルは僕のお気に入りのドラマーのひとりなんだ。本当に驚異的だと思う。
この前、彼のソロ・アルバムを全部聴き直したんだけど、全体的にはかなりポップ寄りというか、無難な路線なんだよね。でも『Face Value』はそうじゃないと思う。それにしても彼のドラムは本当にすごい。僕はずっと思ってきたけど、フィル・コリンズのドラムって本当に驚くべきものなんだ。彼は何でも叩ける。まさにモンスターみたいなドラマーだった。
DM:しかもサウンドも素晴らしいよね、すごくいい音だ。
A:グルーヴも音色も最高だし、それに加えて・・・
(41:35 )
DM:フィルにはウェールズ出身のパッドというドラムテックがいて、彼と一緒に過ごしたのを覚えている。パッドはずっと昔から彼のテックを務めているんだ。 こういう人たちって本当に大事なんだよ。ハウイーをはじめクルーのみんなも、ただスタジオで僕を手伝ってくれたり、一緒にいてくれたりしたよ。これ、言い忘れてたけどすごく重要な事なんだよ。というのも、彼らこそが「これはうまくいってるぞ!」って僕らに感じさせてくれた人たちなんだよ。彼らが「おい、いい感じだぞ、その調子で続けろ!」なんて声をかけてくれた。彼らは何度も僕を支える言葉をかけて、その状況を乗り越える勇気を与えてくれたんだ。
フィルとヒューはコントロールルームにいて、僕はどう作業が進んでるのか分からなかったけど、二人も「いいぞ、順調だ」って言ってくれた。それがものすごく自信につながったよ。 フィルのドラム・テックと、ニューヨーク出身のとても強烈な個性のツアー・マネージャーがいて、でも二人とも励ましてくれて、あまり圧倒されずにやり抜く勇気を与えてくれた。それでも、やっぱりちょっと圧倒されたけどね。だって僕、あの時まで「プレミアリーグ級の現場」なんて経験したことがなかったからね。
A:あの当時、あれほどのアルバムを売った大物アーティストのセッションに参加する機会を得た人はごくわずかでした。あのアルバムだってものすごく売れましたしね。ただ、もうああいう時代は存在しないと思うんだ。だから、あのレベルの世界を経験した人は本当にわずかです。まさに信じられない体験ですよ。
デヴィッド・サンシャス
(42:57)
A:さて、あなたがこれまで共演してきたミュージシャンの中に戻って話をしたいんですが、
いくつか他にもこのチャンネルの視聴者が興味を持ちそうな人たちがいます。その中でもとんでもない「怪物のような存在」だったのがデヴィッド・サンシャスです。彼と一緒に演奏するのはどんな感じでしたか?彼は明らかに『Ten Summoner’s Tales』の時に加わった、とても重要な人物ですよね。
(41:35 )
DM:デヴィッド・サンシャスは本当に素晴らしいミュージシャンです。彼には確かに「彼ならではのサウンド」があって、何よりも彼が重視して夢中になっていたのはサウンド・プロダクション ――つまり壮大な和音の音作りでした。しかも、単なる2音のコードみたいな話じゃなくて、分厚いコードなんだ。たとえば「If I Ever Lose My Faith in You」に出てくるようなコードだ。 彼はそのサウンド自体にとてもこだわっていました。そして彼は独自のボイシングのスタイルを持っているんですが、そのボイシングはかなり密度が高いんだ。でもとにかく、素晴らしい音楽家ですよ。
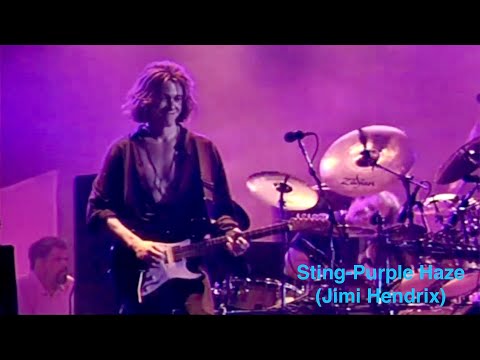
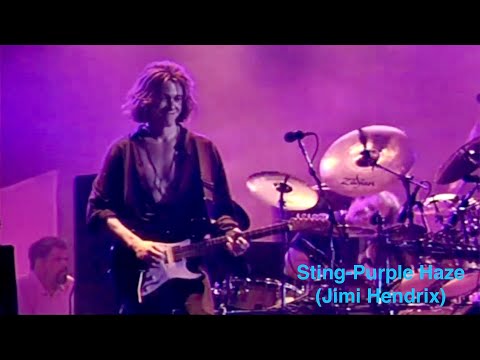
この動画を YouTube で視聴
スティング「The Soul Cages」の時代のメンバーによる、ジミ・ヘンドリクスの「Purple Haze」の演奏。下で話が出てくるが、デヴィッド・サンシャスはギターもとても上手い人で、この曲ではドミニクとツインギターの演奏になっている。ドミニクが加入した、この「The Soul Cages」の時代がスティングのソロのキャリアの中でも、最もシンプルで骨太な男っぽいロックをやっていた時代だろう。
A:それに彼って、ギターも「怪物級に」ものすごくうまいですよね?
DM:そうなんだ。とても優れたギタリストだよ。一時期彼は自分のグループも持っていて、彼を『オールド・グレイ・ホイッスル・テスト』(The Old Grey Whistle Test)で観たことがあります。 (筆者注:「The Old Grey Whistle Test」は1970〜80年代にBBCで放送されていた音楽番組。上のスティーヴ・ヒレッジの動画がその番組のもの。)たしかDavid Sancious and Toneというバンドで、1970年代のものだったと思います。それに、彼は(ブルース・スプリングスティーンの)Eストリート・バンドのメンバーだったし、彼は今では殿堂入りのミュージシャンだよ。
A:そうやって彼はジャズ・フュージョンの世界に入っていったんでしょうね。
信じられないかもしれませんが、Eストリート・バンドのメンバーはみんなジャズ・フュージョンの大ファンだったんです。それで彼がバンドに入った時、ブルース・スプリングスティーンがレーベルにこう言ったらしいんです。「この男を契約しなきゃダメだ。彼はフュージョンの男だ」ってね。
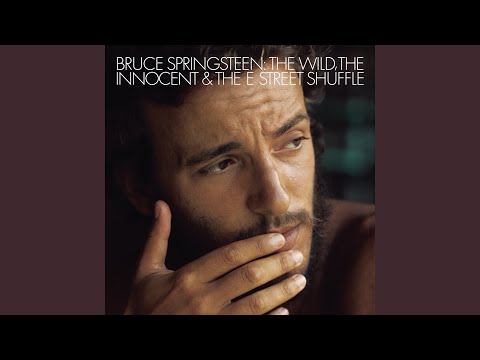
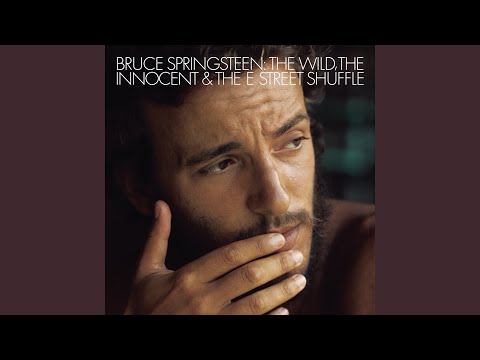
この動画を YouTube で視聴
ブルース・スプリングスティーンの1973年のセカンド・アルバム『The Wild, The Innocent & The E-Street Shuffle 』(邦題:青春の叫び)から。このアルバムで、デヴィッドは八面六臂の活躍をしている。この曲ではオルガン、ピアノに加え、ソプラノ・サックスも演奏している。
(43:29)
DM:彼と一緒に仕事をしたり、ツアーを回ったりするのは本当に素晴らしい経験だった。
ピーター・ガブリエルとの仕事を通じて彼のことを知っていたんだ。彼がどうやってあの独特のサウンドを作り出しているのか、いつも興味がありました。
彼はある意味、ケニー・カークランドとは正反対なんだ。ケニーは音作りにはまったくこだわらないタイプで、ツアー中もいつもこう言っていたよ。「ピアノの音、ピチカートの音、それとシンセのリード音があればそれでいい。音なんてどうでもいいんだ。」とね。
一方のデヴィッドは、シンセやパッドの音を何時間もかけて丁寧に作り込んで、しかも曲に完璧にフィットするんだ。
そういう意味でも、デヴィッド・サンシャスというミュージシャンの最良の部分を特に現していたのが、おそらく『Ten Summoner’s Tales』のアルバムで、スティング作品における彼の最高の演奏のひとつだと思います。彼は一緒に仕事をするのに本当に素晴らしい人物でした。
A:あのアルバムは買わなかったんだ。今は持ってるけどね。CDは買わずに、ビデオを買ったんだ。あの、君がスティングのたくさんあるリビングルームのひとつにいて、そこで撮られた映像(に見える)ビデオテープを持ってたんだよ。いつもそれを見ながら思ってたんだ、「これって口パクなの? それとも本当に演奏してるの?」って。でも、あとで手を加えられてるのかな? それとも本当に演奏してるのかな?あそこで実際何をやってたの? あれも実際のセッションだったの? それとも・・・?
DM:いや、あれはある種の「組み合わせ」なんだ。
アルバム自体はすでに完成してたんだけど、撮影のためにクルーを呼んだ。しかしスティングは口パクをしたくなかった。彼は口パクが大嫌いなんだ、本当に。だから実際に演奏はしたんだけど、ただ、編集のときに演奏映像と録音を組み合わせて使ってると思う。
A:なるほど、組み合わせなんだ。
DM:撮影クルーが何をしたのかはよくわからないけど、俺たちは実際に演奏してたんだ。
A:あの映像、大好きなんだ。だって例えば「If I Ever Lose My Faith in You」なんかの終わりのところで、バンドが一気に広がっていく感じがあって、すごいジャムが繰り広げられてるのが少しずつ聴こえるんだよ。それともうひとつ好きなのは、スティングのコントラバスが倒れて、「ポンッ」って音が実際に聞こえるところだ。
DM:えっ、知らなかった。というか正直に言うと、僕その映像を観たことがないんだ。たぶん一度も観たことがないと思う。
A:ほんとに?
DM:うん、本当に観たことないと思うよ。「Fields of Gold」とか、あのアルバムの曲の映像はいくつかは観たことがあるけどね。YouTubeで誰かが送ってくれたり、たまたま出てきたりして、「わぁ、みんなこんな若くてフレッシュだったんだ!」って思った事はある。「うわ、信じられない。」って。でも、その家のことを思い出したよ。あの家のことはよく知ってる。あの部屋にはたくさんの思い出があるんだ。あの部屋で『Mercury Falling』も録ったんだ。
A:うん、それもビデオで持ってたよ。
DM:あのときも同じような感じでね。みんなで一緒に過ごして、暮らすような感じだった。
僕がずっと想像していた「レコーディングをする」というのはまさにそういうものだったんだ。
同じ家に住んで、一緒に食事して、寝て、スヌーカーをしたり、庭を散歩したり。そういう生活そのものがアルバム制作だと思っていたんだ。フィル・コリンズと一緒にやったときも同じだった。
彼のサリー州のスタジオ——そう、ジェネシスのスタジオだ。あのスタジオにいたとき、「これが本来のやり方だ」と思ったんだ。ロンドンのスタジオみたいに閉鎖的な場所じゃなくてね。
みんなで集まって、一緒に食事して、周りには何もない。やることはひとつ、創造することだけ。そして僕たちは本当にそうしていた。
そして、デイヴィッドは本当に素晴らしいミュージシャンだった。
彼と一緒にツアーをするのはとても楽しかったし、興味深い人だったよ。


この動画を YouTube で視聴
この曲は『Ten Summoner’s Tales』の最後の曲なんですが、とてもハッピーな感じで、演奏しているメンバーの「音楽を心から楽しんでいる感じのまま終わる」ので大好きな曲です。『Ten Summoner’s Tales』のというアルバムの良さは、タイトル通り、沢山の(スティングの)お話が詰まっているような感じで恐ろしくバラエティに富んだ曲調の名曲が収録されています。だから父親を失った後最初の作品で、全編が暗いトーンの、前作の『The Soul Cages』とは全く違います。(もちろん私はそれも大好きです)
Part-2 : 筆者まとめ
ここまでがPart-2の内容になります。まずこの部分の私の結論としては、「みんなみんな、プログレ・ワールド(Prog World)の住人だった」って事でしょうか(笑)プログレ自体がさまざまなジャンルの音楽が融合しているものですし、そこからそれぞれ自分の音楽に発展していったのかな、と感じました。ドミニクも本当は最初はそういうタイプの音楽をやりたかった。それは初期の自主制作盤の『The Latin / Jazz Guitars of Dominic Miller and Dylan Fowler』、『IGAZU』あたりを聞けばよくわかります。でもそれでは食べていけない、という事で、ミュージシャンとして生活するための現実路線としてスタジオ・ミュージシャンになった訳ですが、結局ジェネシス、ピーター・ガブリエルの一派になったのが、なんか面白いなと思いました。
そして、話にも出ていますが、きっとドミニク達の世代が、古き良きロックの時代、つまりCDやレコードがちゃんと売れ、メンバーが一緒に生活なども共にして、時間をかけて音楽を作り上げる事ができた時代の最後の経験者なのかな、という感じは本当にしますね。そしてその黄金時代の感じを、このスティングの『Ten Summoner’s TalesーLive From Lake House, Wiltshire, England, 1993』の動画はとてもよく伝えてくれていると思います。
今、ドミニクが在籍しているECM Recordsなどは、アルバムの録音に2日間しかかけられない。だからやり直しなんてさせて貰えないし、Pro Toolsをいじくり回す時間もありません。それはそれで、確かに音楽の、瞬間に生まれた思いがけない凝縮されたエッセンスを捉えられる、という利点もありますが、ミュージシャンにとっては、いきなり即座にトップギアに入れろ、みたいな話なので、かなーり「力量が試される」部分もあってキツイ面があると思います。ドミニク自身も実際にそう言ってます。
あと、ヒュー・パジャムの音づくりというのは、今聞いても全く色褪せないし、改めて素晴らしいと思いました。次回、Part-3は、冒頭からあのヴィニー・カリウタがオーディションに来た時の話で、爆笑ものです。乞うご期待。
「Little Wing」聴き比べ:最初が1988年、Nothing Like The Sun Tour・日本公演でのジェフリー・リー・キャンベルのジミ・ヘンドリクスの「Little Wing」の演奏。次が同年、ドミニクの「Little Wing」の演奏。これは彼の故郷ブエノスアイレスで行われたアムネスティ・インターナショナル「ヒューマン・ライツ・コンサート」の時で、ドミニクはジミが大好き、しかも会場は彼が大好きなサッカーチームのリーベル・プレート・スタジアムでのライブだったからか、凄い気合いが入ってる感じです!若いこともあって、ドミニクの方がよりロックテイストが強い印象です。


この動画を YouTube で視聴


この動画を YouTube で視聴